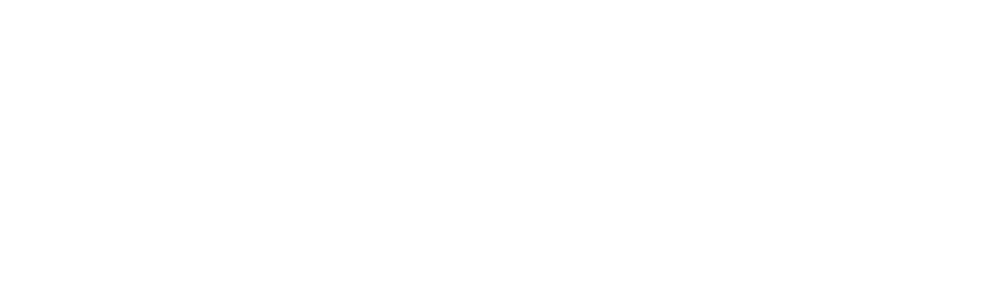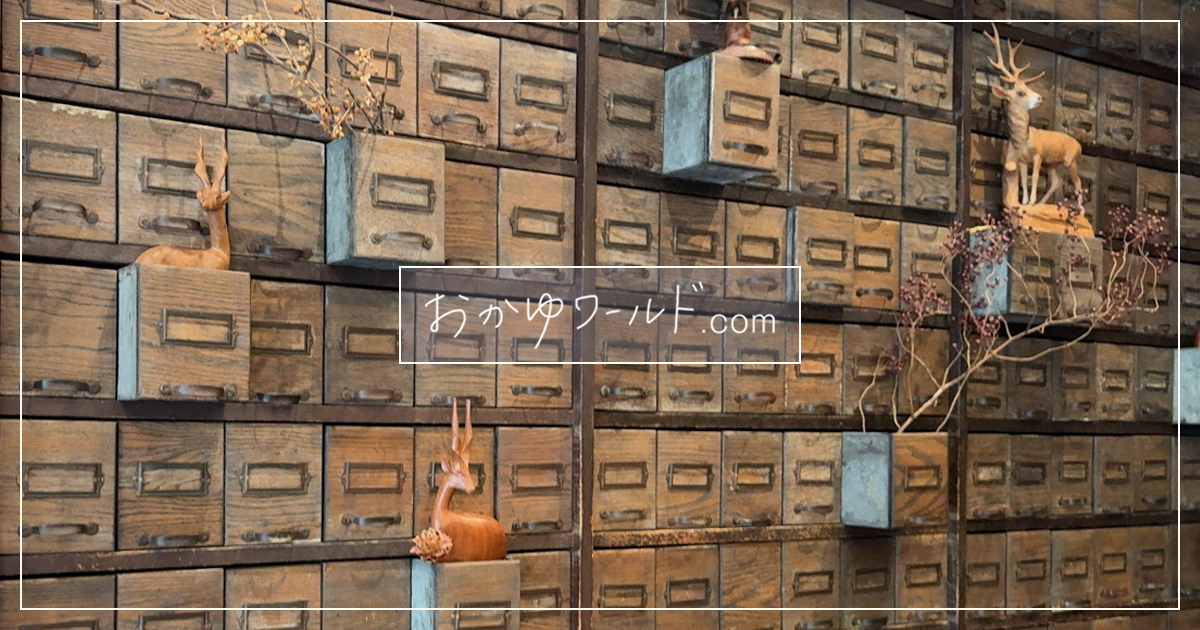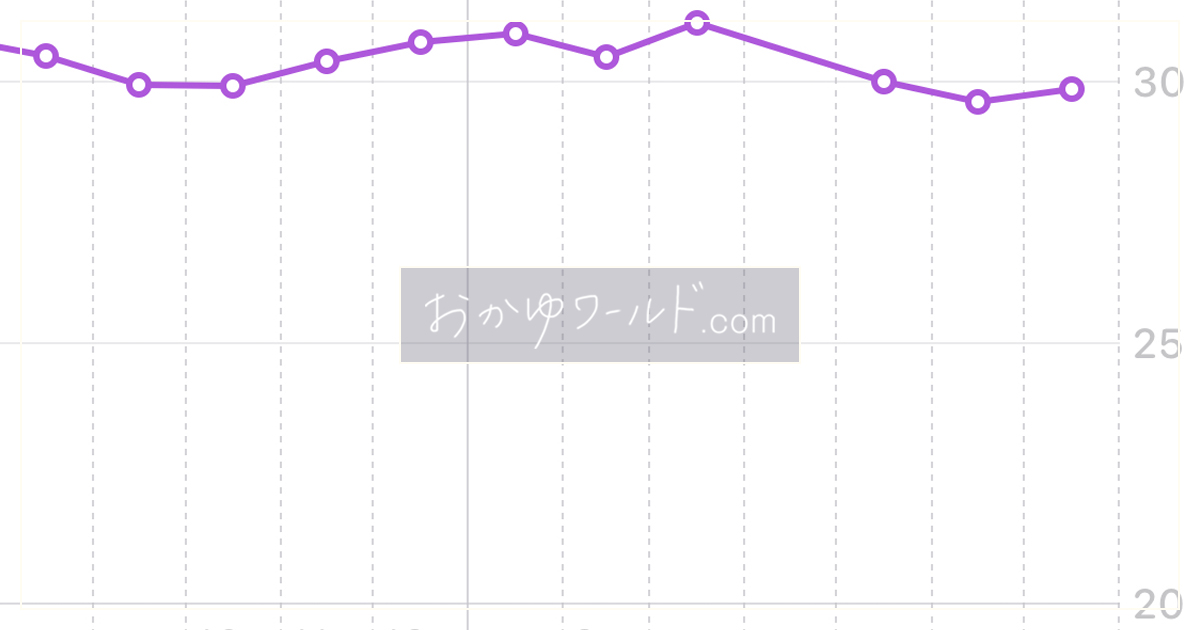説明がつかないものに理由が与えられると、人は、ものすごく安心する。
血液型占いも、MBTIも、「なんか理由がつくとホッとする」人間の心理が生み出した産物なのだろう。
精神的な不調にもラベルを貼ることで、「個人のせい」から「原因のあるもの」に変換できる。
言葉で括ることで、因果関係の構図に落とし込めるものがある。
昔の「狐憑き」も、たぶんそのひとつ。
「何かが憑いている」とすることで、精神的な揺らぎや言動の異常の原因をその人のせいではないとした。
周囲が納得する形に変換する、文化的な免責装置。
見えないもののせいにして人を守る、社会的な赦しのシステムだったのかもしれない。
現代ではどうだろう。精神的な崩れに対してどんなラベルが活用されているだろうか。
まずは大きく「病名」がある。
病名が与えられることで、個人の課題から治療の対象に切り替わる。一般論としての対応策(治療法)、いわばトリセツを獲得することができる。
病名で説明がつかない状態に対しては、どのような回収の仕方があるだろう。
先の、血液型占い・MBTIなどの分類の他に、「病名ではないけれどある傾向をまとめてくれるラベル」がある。社会的な文脈で、社会の関心に応じて、どんどん増えていく類のものだ。
アダルトチルドレン(機能不全家庭で育った生きづらさをもつ人)、ちょっと前に流行りまくったHSP(Highly Sensitive Person/感受性が強く敏感な気質もった人)の概念。ひょっとしたら、ヤングケアラー、ギフテッド、Z世代、といった言葉もこの仲間かもしれない。
いままで個人の特性とされていたものが、ある条件下で、多くの人にとっての共通項だったと発見される。
ラベルとなることで、自分だけの固有な異常ではないと納得することができる(または、この特性に対してつらいと感じていいのかと気づきになる)。他者と共有できる形になり、対応策や仲間をみつけやすくなる。
構造の言語化が達成され、多くの人にとって「なるほど、だからこうなのか」と腑に落ちる安心が与えられる。
腑に落ちる形に変換され、文化的な免責装置となる構造は、先の狐憑きとまったく同じだ。
病名でもない、分類にあてはまる特性でもない、社会的な関心でラベル化されたものにもあてはまらないものに対しては、どんな回収があるだろう。
わたしは最近「自律神経の乱れ」がそれに近いような気がしている。
病名までいかない微妙にツライ症状を調べると、たいてい自律神経の乱れ、と説明される。
原因が自律神経の乱れだとされることで何かがすぐに解決するわけではないのだけれど、なんとなく腑に落ちるというか、「あ〜、自律神経の乱れか〜」と納得にも似た感情を得ることができる。
でも、冷静に考えると、全然説明になっていないことも多々ある。
たとえば、眠れない理由を調べると「自律神経の乱れ」。そして、自律神経の乱れの理由を調べると「寝不足」。……みたいな完全に堂々巡りに陥ったりする。
それでも私は、説明にならない説明にもなんとなくの安心を見出すことができる。
つまりラベルは、因果の正確さよりも「納得できる形」を与えることに価値があるのだ。
なんかよくわからないけど、狐憑き。
なんかよくわからないけど、自律神経。
理由が与えられると安心する。
それは人間の弱さかもしれないし、社会の知恵かもしれない。
ラベルとは、きっと「わからなさ」と共に生きるための道具なのだ。