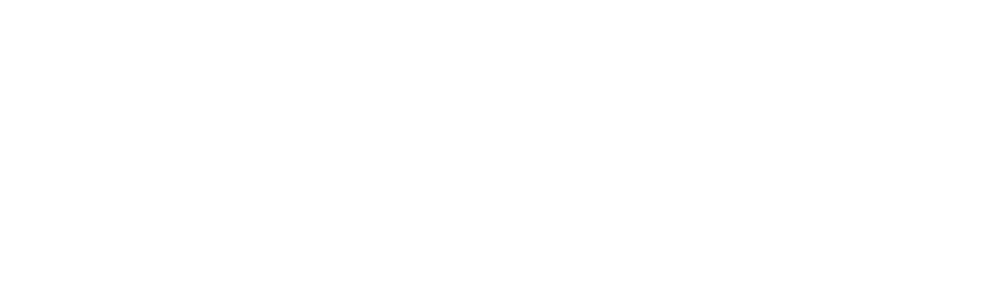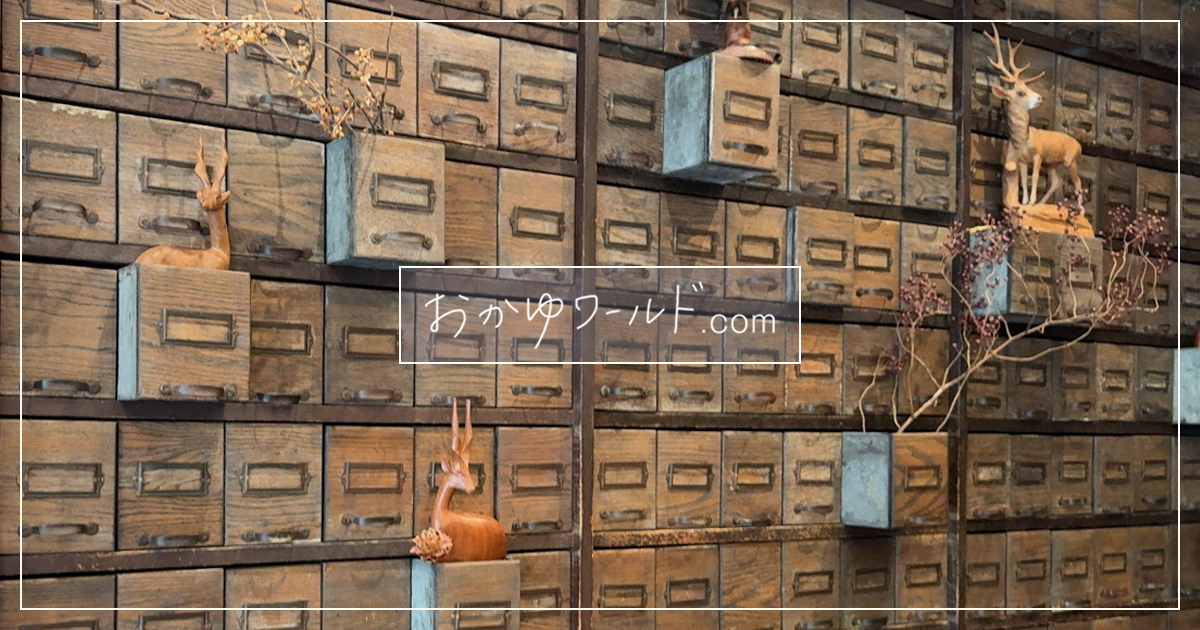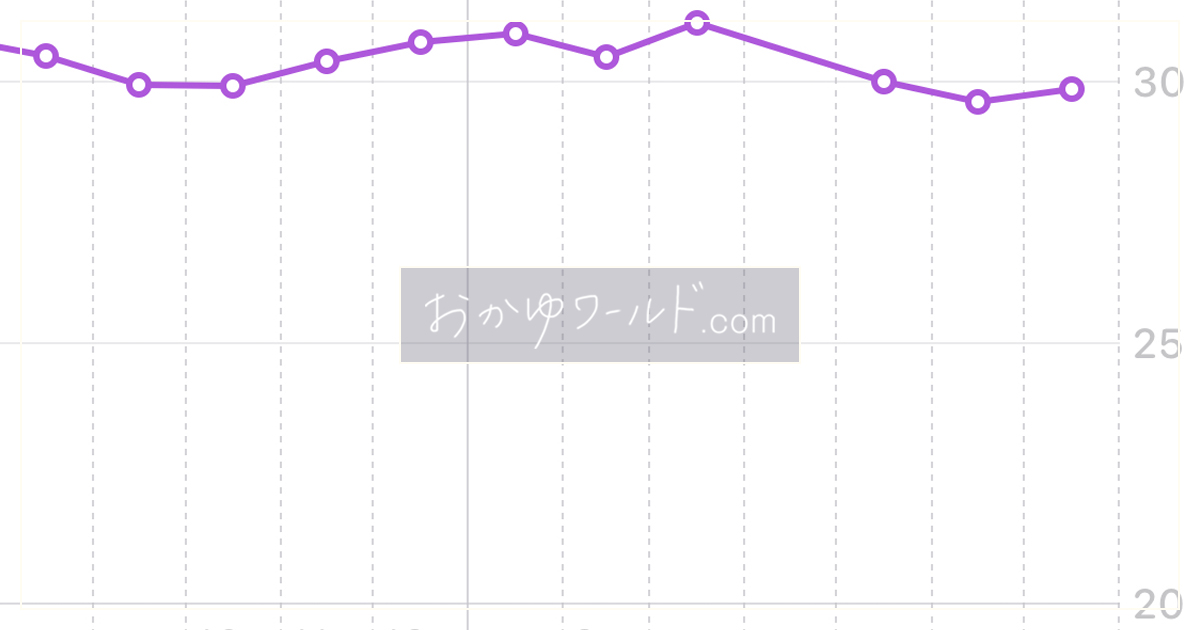ラー油のボトルキャップのデザインに、モヤモヤしている。
あの、オレンジ色のキャップの、エスビー食品の「辣油」についてである。
ハイテクファミレスに適応しながら、ラー油が出せない
モヤモヤのきっかけとなったのは、ものすごく久しぶりにバーミヤン行ったことだった。
用事と用事の合間のランチで、時間的にそのバーミヤンかコンビニか……だったから、せっかくならと、たぶん人生3回目くらいのバーミヤンに行ってみたのだった。
駅からは外れのそのバーミヤンは、地元の人が集まりやすい立地なのだろう。店内は、3〜4人組が3組ほど。それ以外は1人客で、パソコンやスマホをいじりながらの働く世代が半分、もう半分は定年後と思われる年代の一人客だった。8割埋まりの盛況ぶり。
たまたま壁側の席になったので、ぼーっと店内を眺めながら食事していた。
ななめ前の男性。70代だろうか。手慣れた様子でタブレット使い、オーダーを済ませると、すぐにセルフサービスの水を取りに席を立った。店の配置も、仕組みも、全て「日常」と言う感じのスムーズさ。
あっという間に料理が届く。男性は配膳ロボットから料理を取り出し、OKボタンを押す。
定食と、ランチの小皿餃子。餃子のタレをつくろうと、調味料台から醤油を取り出し、小皿に注ぐ。次にラー油を取り出し、小皿の上でひょい、と振る。

しかし、出ない。
ラー油が出ないのだ。
何度か小皿の上でラー油の小瓶を振る。ボトルのキャップを閉めて、上下に振り、もう一度小皿の上で振る。
それでも、出ない。
男性はまあいいかと諦めた様子で、食事が始まった。
ラー油の出し方の正解は、フタをあけた後、ぷにっとした「押しボタン」を押す、だった。

……ちなみにここまでの流れ、わたしは男性の背後から景色のように眺めていたので、突然後ろから声にかけるのも不自然に思えて……特段の働きかけはしなかった。できなかった。(席の間隔が狭い「街の食堂」みたいな感じで席が隣ならね、ぜんぜん「ここ押すんですよ〜!って言えるけどさ……)
とても便利な「押しボタン」
日本一のシェアを誇ると言う、エスビーのラー油。
我が家にももちろんある。
しかも購買の理由は「このキャップがあるから」である。
お粥研究家的にはトッピングとして1滴のバランスを考えたい場面も多く、「押しボタン」が付いているエスビーのラー油はマストの調味料なのだ。
エスビーのサイトによると、この「押しボタン」はユーザーからの要望をもとに押しやすさの改善も図るなど、かなりの肝入りパッケージであることが伺える。
しかし先の場面では、押しやすさ云々という話ではなく、そもそもキャップを開けたあとに「どこかを押す」ということに注意が向いていないようだった。
この便利は、ほんとうに便利、なのだろうか?
わたしにとっての便利は、みんなにとっての便利ではないのかもしれない
繰り返しになるが、わたしはエスビーのラー油のボトルの仕組みが大変気に入っている。
液ダレしにくいし、辛味も抜けにくい。なんといっても調整しやすい。オリーブオイルとか、タバスコとか、いろんなものがこのパッケージになればいいのにとすら思っていた。思っている。
しかし、バーミヤンでのあの場面を振り返ると、このデザインはいわゆるバリアフリーでも、ユニバーサルデザインでもないのだろう。
「ユニバーサルデザインとは、文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの個人の違いにかかわらず、出来るだけ多くの人々が利用できることを目指した建築(設備)・製品・情報などの設計(デザイン)。」(Wikipedia)
それどころか、使いやすさ以前に、調味料を出したい時に出せない(使えていない)ことは、デザインとして大きな欠落を抱えているのかもしれない。
極端な話、ドバッと出てしまったり、ダラダラたれてくるほうが、「誰もが使える」という意味では、調味料という目的は果たすことができる。
2020年代のハイテクファミレスを日常にする70代くらいの方(間違いなく平均寿命より若い方)が、直感的に使えない調味料のパッケージって、ありなのかな?
「押す」という文字がまだ読めない、子どもは使えるのかな?はじめて日本にくる海外の人は?

まとめ:わたしは何がショックだったのだろう
あの男性は、ラー油のない餃子を食べ続けるのだろうか。不審者に思われても食事中の背後から教えてあげるべきだったのだろうか。
わたしは、何がショックだったのだろう。
自分にとって便利革命だったものが、誰かにとっては不便になっていることがあるという事実が、ショックだった。
「便利すぎることでついていけない人が発生するかもしれない」「私にとっては便利でも全ての人にとっての便利ではないのかもしれない」こういう視点がなかったことにも、ショックだった。
でも、きっとわたしは、エスビーのラー油を買い続ける。でもそれって、「バリア」に賛成してるってことなのかな。
うーん、うーーーーん。
そんな、モヤモヤが続いている。